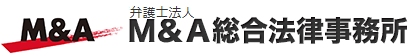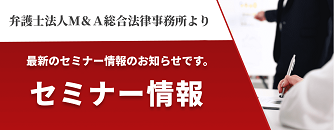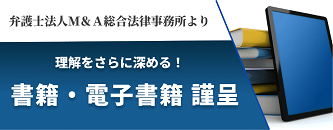従業員が労働審判を申し立ててきた!
「従業員から労働審判の申立書が届いた。どのように対応すれば良いのだろうか」
「労働審判の申立書という分厚い用紙が裁判所から送られてきた。どうすれば良いのだろうか」
とお悩みではありませんか。
結論から申し上げますと、1秒でも早く弁護士に連絡を取り対処するようにしましょう。
なぜなら、労働審判は通常の裁判とは異なり、スピード勝負が求められる制度となっているためです。
通常の裁判が半年から1年かかることを想定した長期戦(労働裁判では1年以上になることもあります)なのに対して労働審判は90日以内に決着を目指す制度となっています。
そのため、第一回目の労働審判期日にしっかりとした証拠と反論を用意しなければなりません。
また、裁判と労働審判は大きく異なる点があります。
裁判(民事訴訟)は徹底した証拠書面で勝負するのに対して、労働審判では口頭での陳述がメインで進行していきます。
つまり、労働審判の申立書を弁護士と共に入念に読み込み話す言葉などを決めておく必要性があります。
この記事を読むことによって、労働審判の流れと対応方法について理解することができます。
労働審判を申し立てられて戸惑っている方はぜひ、最後まで読んでいって下さいね。
⇒元従業員の労働審判でお困りの方はこちら!
労働審判とは
労働審判とは企業と従業員(元従業員を含みます)の間で生じた労働紛争について裁判所で話し合いを行うための制度です。
労働審判は労働紛争のスピード解決を目指した制度であり、3か月(90日以内)に労働問題の解決を行う制度となっています。
全部で3回の審判によって決着する制度となっていますが、1回目の期日は労働審判の申し立て日より40日以内に指定されることになります。
1回目の期日が最も重要だというのに、短い期間で準備をしなければなりません。
また、原則として1回目の期日を経営者側の都合で動かすことはできません。
もしも労働審判で解決できなければ労働審判から裁判に移行することになります。
事案にもよりますが、出来る限り入念に準備を行い、裁判移行して長期化する前に労働審判の段階で解決をした方が良いでしょう。
労働審判が90日以内に決着するのに対して、裁判は半年から1年以上判決までに時間がかかることもあるためです。
また、地方裁判所の第一審で決着すれば良いですが高等裁判所への控訴が起こりえることを考えると1年どころでは済まない可能性もあります。
労働審判では労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名(経営者側1名、労働者側1名)で構成される労働審判員の前でそれぞれの意見をぶつけ合います。
書面が重要視される裁判とは異なり、労働審判では口頭での話し合いが重要視されます。
労働審判員の前でうっかり違法なことを当然だと認識して主張し、感情的な言動を行ってしまうと不利になる可能性があります。
原則、弁護士と一緒に出席するようにしましょう。
苦手な部分は弁護士に任せることが可能です。
労働審判で経営者側が本人訴訟するのは危険
労働審判において経営者側が本人訴訟をするのは非常に危険です。
なぜなら、労働審判は書面と口頭の両方で進んでいくためです。
「難しい書類を出すわけではないし、話し合いの場なのだから、本人でやっても問題ないでしょう」と思われるかも知れません。
しかし、本人訴訟では不利になることが多くなります。
法的な知識だけではなく仮に経営者側が正しいと思っていることでも厳密に法律に照らすと「これは違法行為だ」と指摘されるようなものもあるためです。
また、労働審判が不調に終わると裁判が開始されます。
つまり、最初から裁判を見据えて進めておかないと裁判移行したときに対応できなくなります。
弁護士に依頼すればもしものときのリスクを織り込んだ書面作成や労働審判の進行をしてくれます。
先を見据えて弁護士に相談するようにしましょう。
労働審判の流れと注意点
「労働審判はどんな流れで進んでいくの」と気になりませんか。
労働審判は、具体的には以下の流れで進んでいきます。
- 労働者側が裁判所に対して労働審判の申立書を提出
- 裁判所から会社側に労働審判の申立書を郵送し会社側が受理
- 会社側が裁判所に対して指定日(第1回期日の1週間前まで)に答弁書や証拠書面、反論を提出
- 審理 第一回目期日
- 審理 第二回目期日
- 審理 第三回目期日
それぞれについて解説します。
労働者側が裁判所に対して労働審判の申立書を提出
労働者側が裁判所に対して労働審判の申立書を用意して送付します。
労働審判の申立書を裁判所は労働審判にふさわしいかどうかを判断し問題なければ受理します。
申立書を裁判所が受理してから40日以内に1回目の労働審判の日が指定されます。
労働審判においては申し立ての段階で証拠を全てそろえておく必要があり、証拠書類として以下のような書類が送付されてくる可能性があります。
- タイムカード
- 就業規則
- 雇用契約書
- 解雇理由書
- 解雇通知書
上記のような書類が添付されて相手方の主張と共に裁判所に送付されます。
特に入社時に配布している就業規則や雇用契約書を根拠に裁判を起こされることが多いため、雇用契約書と就業規則が送られる確率は高いです。
裁判所から会社側に労働審判の申立書を郵送し会社側が受理
労働者側から裁判所に対して労働審判の申立書を郵送し、会社側が受理します。
会社側からすると「いきなり裁判所から分厚い書類が送られてきて、中身をよく読んでも身に覚えがない」というケースがあるため混乱することが多いです。
注意点として会社側に書類が到着した段階において社内で会社の関係者を集め事件についての証拠を集めると共に、弁護士に連絡することが重要です。
最初から弁護士に依頼を行えば必要な証拠などを弁護士が指示してくれるためです。
労働審判では1回目期日までにどれだけしっかりとした反論をまとめるのかが重要になります。
「弁護士に相談しようか」と迷っている間にあっという間に労働審判の日が近づいてきます。
早期の段階で弁護士に相談し、的確な指示のもとに証拠書類や関係者からのヒアリングを行うようにしましょう。
会社側が裁判所に対して指定日(第1回期日の1週間前まで)に答弁書や証拠書面、反論を提出
会社側が裁判所に対して指定日(第1回期日の1週間前)までに答弁書や証拠書面・反論を提出します。
労働審判の日の1週間前までに書類を送付しなければならないため、実質30日程度しか時間がありません。
かなりのスピードで証拠集めや反論の作成を行わなくてはならず、弁護士なしでは苦戦を強いられます。
審理 第1回目期日
労働審判の審理の第1回目期日ではお互いの提出した証拠を元に口頭ベースで審判がスタートします。
スピード決着を目指した制度であり、1回目に出来る限りの主張をしなければなりません。
ただし、労働基準法上間違ったことを経営者が言ってしまうと「それは間違っています」などと労働審判員から指摘されて不利になることもあります。
事前に弁護士と打ち合わせを重ねておき「知識的にあやふやな部分は話さない」という取り決めをして労働審判に挑むことが重要です。
ちょっとした発言から相手に足をすくわれることもあります。
また、和解すれば第1回目期日で労働審判を終えることも可能です。
1回目で和解が不成立ならば2回目に持ち越されます。
審理 第2回目期日
審理第2回目期日では第1回目で話した内容を元に、争点整理や原告・被告への聞き込みがなされます。
争点整理が終わり、和解が成立すれば終わりです。
和解が不成立なら3回目に持ち越されます。
審理 第三回目期日(決着)
労働審判の審理3回目でいよいよ決着がつきます。
和解ができなければ労働審判委員が結論を出し、審判を下すためです。
「不利な内容で審判になってしまったらどうしよう」と悩まれる方もいるかも知れませんが、労働審判の審判に納得がいかない場合は裁判へと移行します。
注意点として、労働審判は世間に知られることはありませんが、裁判移行すると世間に知られる可能性があります。
また、裁判移行する場合も労働審判で出た審判の内容が重視されることがあります。
早期の段階から弁護士に依頼し、和解を視野に入れて対応することがおすすめです。
労働審判を会社側(経営者側)から従業員に仕掛けることは避けよう
労働審判を経営者側から労働者側に対して仕掛けることは出来るだけ避けるようにしましょう。
なぜなら、反訴されて裁判移行する可能性が高くなるためです。
労働審判を経営者側が起こした場合、相手方(労働者側)が同じ事件について地方裁判所で本裁判を起こすといきなり本裁判に突入する可能性があります。
労働審判の仕組みとして労働審判の結果が気に入らない場合、裁判移行することになります。
経営者側が起こした労働審判の結果を労働者側が受け入れないのは当たり前のため、いきなり本訴訟を定義されるリスクが高まります。
ごくまれにですが、経営者側から労働者側に対して労働審判を申し立ててしまうことがあるのです。
労働者から労働基準法上の不備を指摘され、労働審判に至るまでの過程でプライドを傷つけられて労働者に対して復讐心から労働審判を起こしてしまうというケースです。
労働者側から一方的に避難されて怒りが蓄積することは理解できますが、労働審判を経営者側から起こしても得をすることはないと言っても過言ではありません。
地位不存在確認で労働審判を起こしたところで、労働者から得られる債権は存在しません。
しかも企業側による恫喝訴訟(スラップ訴訟)などと騒がれて悪い評判が立つことにもつながっていきます。
労働審判を経営者側も申し立てることが制度設計上可能になっていますが、原則、労働者側が労働審判を起こすことが一般的となっています。
経営者側から仕掛けるよりも、労働者側から労働審判を仕掛けられることを待った方が得策です。
従業員から労働審判を起こされるかも知れない4ケース
「身に覚えのないことで労働審判を起こされることはあるのだろうか」と気になりませんか。
労働者側と経営者側で認識がズレていると「こんなことで訴えられてしまうのか」という問題が起こりやすくなります。
労働審判は労働者が利用しやすく設計されており、以下のような労働問題が起こっていると労働審判を起こされる可能性があります。
- 社員を解雇した
- 残業代未払いをした
- 契約社員を雇止めした
- 社員の降格と減給を行った
それぞれについて解説します。
社員を解雇した
正社員を解雇した場合、労働審判を起こされる可能性があります。
なぜなら、正社員の解雇は認められにくいためです。
正社員の解雇は非常にハードルが高く、しっかりとした理由がなければ厳しいです。
正社員を何らかのことで解雇した場合、突然労働審判を起こされる可能があります。
残業代未払いをした
残業代未払いをした場合、元社員や社員から労働審判を起こされる可能性があります。
労働基準法上、残業をした場合には割増賃金を支払う必要性があるためです。
残業代未払いの場合は経営者や管理職が見ていないところで社員が実は残業をして記録をつけていたというケースもあり、訴えを起こされるまで原因が分からないこともあります。
残業時間の管理や、繁忙期以外は定時で上がるなど労務管理を普段から入念に行う必要性があります。
契約社員を雇止めした
契約社員を雇止めした場合、労働審判を起こされる可能性があります。
契約社員といっても雇止めには一定のルールがあるためです。
例えば、仕事がなくなってしまったから契約期間が残っているにも関わらず解雇してしまったりするケースでは認められないことが多いです。
また、仮に契約が終了していたとしても3年間を超えて労働契約を更新し続けている場合には雇止めが難しくなることがあります。
「なんとなく契約満了だから」といって雇止めをするのではなく、出来れば弁護士等の専門家の意見を聞いて契約終了を通知できるのかどうかを判断した方がトラブルを防ぐことができます。
契約社員に対して期間満了後に退職金を支給するなどして納得感をもって退職をしてもらうという方法など、契約社員が気持ちよく会社を辞められるような体制を気づくことも大切です。
社員の降格と減給を行った
社員の降格と減給を行った場合、労働審判を起こされる可能性があります。
特に正社員に関して役職そのものの降格は認められても給料を下げるということは認められない可能性が高いためです。
賃金の減額を伴う降格などには細心の注意を払い、どのような方法であれば法律的に問題ないかを考えるようにしましょう。
合法的な賃金減額や降格の方法が分からない場合、弁護士に依頼してサポートを受けることをおすすめします。
いきなり賃金の減額をしてしまった、という心当たりのある経営者は要注意です。
労働審判を弁護士に依頼するメリット
「労働審判を弁護士に依頼するメリットは何なのだろうか」と気になりませんか。
法律の専門家である弁護士に労働審判の対応を依頼することで法的に会社が誤った対応をしている部分と、労働者が勘違いしている部分を精査することができます。
弁護士の指摘であれば的確な上、素直にアドバイスを受け入れられることもメリットです。
他には、以下のようなメリットがあります。
- 早期解決が実現する可能性が高くなる
- リスクを回避できる
- 安心感をもって労働審判に出席することができる
それぞれについて解説します。
早期解決が実現する可能性が高くなる
労働審判を弁護士に依頼することによって、早期解決を実現することができる可能性が高くなります。
なぜなら、労働審判に精通した弁護士は案件ごとに落としどころ(和解金の相場など)を知り尽くしているためです。
労働審判で最も避けたいことは、労働審判でうまく決着がつかずに本裁判に移行してしまうことです。
経営者はただでさえ仕事が忙しいのにも関わらず裁判を抱えることになれば、仕事に集中できなくなります。
早期に労働審判で決着をつけ、会社の評判に傷をつけずに終わらせることが最も重要です。
リスクを回避できる
弁護士に労働審判へ同席してもらうことによって、余計なことを言ってしまうリスクを減らすことが可能です。
労働審判は早期決着を目指した制度であり、口頭で争点を整理する制度のためです。
よくあるケースとして感情的になってしまいうっかり言わなくても良いことを言ってしまう経営者の方がいます。
例えば残業代請求の労働審判で経営者が「タイムカードは5分単位で付けているから法律的に問題ないだろう」というような主張をしてしまうケースです。
タイムカード上は労働時間が5分刻みで切られていたとしても、実際の法律上、残業代は1分単位で残業代を支払うことを求められています。
下手をすると労働審判員から「残業代は1分単位で支払わないとダメなんですよ」と諭されるようなことになり、一気に印象が悪くなることもあり得ます。
弁護士に依頼し同席してもらうことで不用意な一言を減らすことができます。
また、法律に関して全く自信がない場合、重要なところは弁護士に話してもらうように対応することもできます。
安心感をもって労働審判に出席することができる
法律のプロフェッショナルである弁護士が労働審判に同席してもらうことで安心感をもって労働審判に挑むことができます。
労働審判は原則、当事者以外は弁護士しか同席を認められていないため、弁護士以外の第三者を入れることができません。
会社側の関係者を労働審判に出席させることは可能ですが、人選を失敗すると聞かれたくない社内事情まで社員に聞かれてしまうことにもつながります。
弁護士には守秘義務がありますし、依頼者を守るために必ず仕事をしてくれます。
労働審判を起こされたら素早く弁護士に依頼をするようにしましょう。
労働審判の内容を社員や経営者以外の役員に知られたくない、というケースでは経営者本人以外が労働審判に出席することが出来なくなります。
1人だけで労働審判に挑むよりも弁護士がいた方が安心できます。
⇒元従業員の労働審判を解決する方法を見る!
労働審判を弁護士に依頼するデメリット
「労働審判を弁護士に依頼するデメリットはなに」と気になりませんか。
労働審判に関して弁護士に依頼するデメリットは実はあまりありません。
ただし、少しだけ以下のようなデメリットがあります。
- 本人訴訟よりも費用がかかる
- 丸投げできるわけではない
それぞれについて解説します。
本人訴訟よりも費用がかかる
労働審判を弁護士に依頼するデメリットとして、経営者だけで対応する本人訴訟よりも費用がかかるという費用面のデメリットがあります。
本人訴訟であれば弁護士を雇うよりも費用がかからないため経済的に良く見えます。
ただし、労働審判がうまくまとまらなかった場合に事件を受任してもらう弁護士を探すことが難しいという問題があります。
労働審判がうまくまとまらなかった場合、裁判となります。
労働審判の結果は裁判官にもよりますが、本裁判に影響することが多々あります。
すでに負け筋となってしまっているような状態で弁護士に受任依頼をしても受任拒否される可能性が高くなります。
裁判移行してしまった場合に備えて、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。
丸投げできるわけではない
弁護士に依頼をしても丸投げできるわけではありません。
手間を省くために弁護士に仕事を外注するという感覚で仕事を依頼するのではなく、会社を守るために経営者自身も動く必要性があることを理解する必要性があります。
民間企業の感覚では外注した場合は外注先がほぼ全ての仕事を代行しますが、労働審判でうまく和解するためには証拠書類の収集などの作業が必ず出てきます。
また、口頭ベースで労働審判が進行するため当日の打ち合わせも必要となります。
何を話すのか、反対に絶対に口にしないようにした方がいいことを弁護士と打ち合わせます。
本人訴訟で全ての証拠を集めるよりも事件の経緯を来た弁護士が精査し「この証拠書類を下さい」という形で指示を出してくれます。
効率的に労働審判を迎えることができるため、弁護士に最初から依頼することが重要です。
労働審判が裁判移行して他の従業員に知られると起こり得るトラブル拡大
「労働審判が裁判移行すると、他の社員にバレる可能性があるというけど、何が問題なの」と気になりませんか。
結論から申し上げますと、他の社員が労働審判や裁判の内容を知ることで同じような労働審判や訴訟を何度も起こされる可能性があります。
労働審判を起こされて裁判移行し、他の社員が知るところとなると以下のようなことが起こります。
- 他の従業員が労働審判を起こす
- 会社に不信感を持ち、法的な欠陥を探す社員が増加する
- 元社員から同じような内容で労働審判を起こされる
それぞれについて解説します。
他の従業員が労働審判を起こす
裁判移行することによって他の従業員も労働審判や裁判を起こす可能性があります。
「彼がやったのなら私もやってみよう」と思われてしまうためです。
1人が裁判を起こしたことを知り、同じような不満を持った社員が次々に出てくることは避けなくてはなりません。
本業に集中できなくなります。
会社に不信感を持ち、法的な欠陥を探す社員が増加する
社員が裁判を起こしたことが周囲に分かると、会社に対して社員が不信感を抱く可能性が高くなります。
そのため、会社の法的な欠陥について探して回るような社員が増える可能性があります。
労働基準法に詳しい社員が増えることによって経営者の想いと社員の想いが離れていき、円滑な事業運営が行えなくなる可能性が高まります。
出来るだけ労働審判の段階で早期終結させ周囲の社員に知られないようにすることが大切です。
元社員から同じような内容で労働審判を起こされる
労働審判が通常訴訟に移行することによって、元社員から同じような内容で労働審判を起こされるリスクが高まります。
特に残業代の未払い訴訟などです。
残業代の未払いは時効が存在しますが、期限内であれば訴訟を起こされるリスクがあります。
「前にいた会社、残業代未払いで訴えられたらしい。300万円くらい会社が支払うことになりそうだ。そういえば、私も結構残業していたな」などと元従業員が考えると何度も裁判や労働審判を起こされることになります。
特に従業員同士の横のつながりが強く、退職後も現職の社員と何らかの連絡を取り合うような企業であればリスクは増します。
何度も裁判や労働審判を起こされると金銭的な厳しさだけではなく精神的にも追い詰められます。
従業員からの労働審判をきっかけに顧問契約を結ぶ企業も多い
「労務トラブルが起こらないようにしたいと思っても、うちには人事部すらない」と思っている経営者の方は多いです。
人事部門がある会社は労働基準法違反にならないような事業運営の方法などでリスク回避が可能です。
一方、人事部は間接部門であり、お金を生まない非生産部門のため中小企業では雇用することが難しいという側面があります。
そこで、弁護士と顧問契約をしておくことが重要となります。
弁護士と顧問契約を締結することによって以下のようなメリットがあります。
- 顧問契約をしておけば訴えられたときに即座に弁護士に連絡可能
- 労務トラブルの火種を消すことができる
- 特に人事部がないまたは少ない企業は大きな労務管理リスクを軽減できる
それぞれについて解説します。
顧問契約をしておけば訴えられたときに即座に弁護士に連絡可能
弁護士と顧問契約を締結することによって、社員や元社員から訴えられたときにすぐに弁護士に連絡することが可能です。
「訴えられてから弁護士を探しても良いのではないか」と思うかも知れませんが、顧問契約をしておくと「受任してもらえるのかな」という不安がなく即座に相談することができるため安心です。
どれだけ手を尽くしていても労務トラブルが完全にゼロになることはなく、従業員との衝突を避けられないことがあります。
大企業の人事部門でも訴訟に移行しそうな案件や労働審判を起こされた場合には顧問弁護士に連絡をして対策を練ることが一般的です。
労務トラブルの火種を消すことができる
弁護士と顧問契約を結ぶことによって、気軽に電話やメールで弁護士に相談することが可能です。
労務トラブルのほとんどは初歩的なところから始まるため、普段から弁護士に相談しておくことで防げることは多いです。
例えば、社員の異動や、残業申請のフロー、懲戒解雇、普通解雇などです。
「正社員なのだから異動するのは当たり前だろう」と思われるかも知れませんが、育児介護休業法の改正などで育児や介護にあたる従業員を異動させることが難しくなっています。
また、残業も「なんとなくさせている」という状態は危険です。
残業は部下が上司に申請して許可を貰ってから残業してもらうといった体制づくりをしないといくらでも残業代を請求されてしまうためです。
解雇も「こんな犯罪まがいのことをすれば当然解雇だろう」というような感情的な解雇をすることは難しいです。
経営者が社員の処遇に関しての決定をするとき、顧問弁護士がいれば相談し、リスク回避しつつベストな方法を提案してもらうことができます。
特に人事部がないまたは少ない企業は大きな労務管理リスクを軽減できる
顧問弁護士は人事部がない企業や、人事部員の人数が少ない企業で労務管理リスクを軽減できるというメリットがあります。
人事部がなければ普段から労務管理を適法に運用することが難しいためです。
また、人事部が存在していたとしても人数が少なければ給与計算や賞与計算・社会保険の届け出業務などの計算や書類提出が中心となっていると労務管理をしっかりと行うことは難しくなります。
顧問弁護士をつけることで、労務管理のアドバイスを受け改善することができるため、結果的には人事部員を雇用し、増員するよりも安価で労務管理を行うことができます。
顧問弁護士を活用し、労務管理の充実を図るようにしましょう。
⇒元従業員の労働審判でお困りの方はこちら!
まとめ
今回は、従業員から労働審判を申し立てられた場合の対処法について解説しました。
特に本文中でも解説させていただきましたが、労働審判は早期解決を目指した紛争解決制度となっており、1秒でも早く弁護士への相談が必要となります。
会社に労働審判の申立書が届いてから、約40日内に初回の期日が指定されます。
しかも、1回目の労働審判の審理の日の1週間前までに反論の書類を送る必要性があります。
また、3回の中で和解成立しなければ審判に移行し、審判に異議があれば裁判に移行します。
裁判に移行してしまうと世間に従業員とのトラブルの内容が知れ渡り、他の従業員から訴訟を起こされるリスクも高まります。
労働審判を起こされた時点で弁護士に相談し、早期解決を目指しましょう。
⇒元従業員から不当解雇を言われお困りの方はこちら!