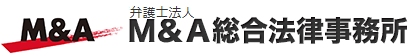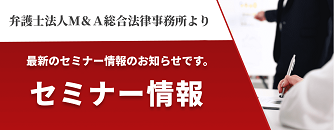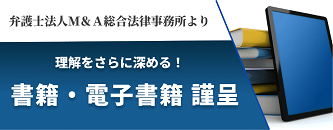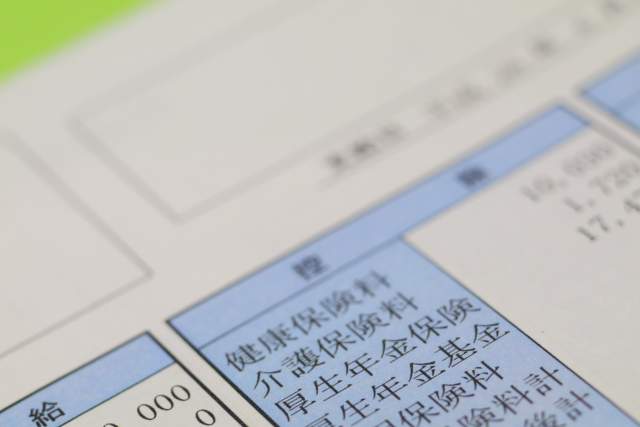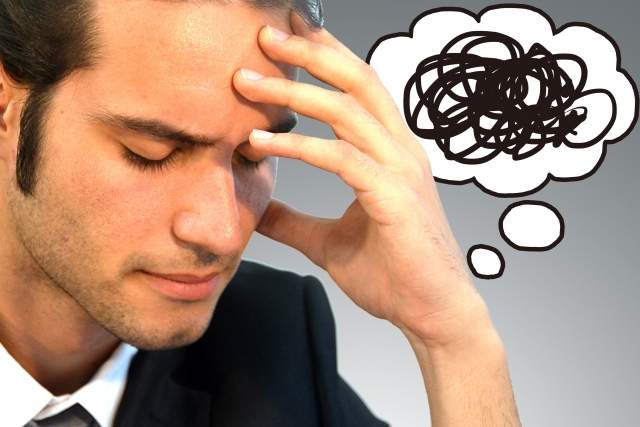M&A労務デューデリジェンス(DD)の視点
M&Aの最終契約書には、人事労務デューデリジェンス(DD)を踏まえて、下記のような人事労務に関する表明保証を規定する。この表明保証との関連で、人事労務デューデリジェンス(DD)の視点を、以下説明する。
⇒問題社員にお困りの方はこちら!
労使紛争等の不存在(1)対象会社には、重大な労働争議は存在せず、また、労働組合は存在しない。(2)従業員に関して、支払期限が到来した未払賃金・退職金その他の報酬、又は社会保険料は存在しない。(3)対象会社は、労働関連法規(労働基準法及び労働者災害補償保険法を含むがこれに限らない)を、遵守している。 |
第9号(1)は、労使紛争等の不存在に関する表明保証である。
労働関連法については、近似、長時間労働や過労死の問題、未払い残業代請求訴訟の乱発、働き方改革などの法律問題や法改正の多い分野であり、実際、事業承継M&Aに際しても、従業員に関する紛争は頻発している。
その中でも、存在した場合に特に大きく対象会社の企業価値を毀損するものが、労働争議や労働組合の介入である。
事業承継M&Aの対象会社である中堅企業・中小企業において、労働組合が存在している事例は多くはないものの、存在している場合、労働組合に対する対応は、対象会社においては大きな負担となるため、労働組合が存在するか否かは、対象会社の企業価値を検討する際に大きな問題である。
また、中堅企業・中小企業において、労働組合が存在している事例は多くはないものの、労働組合が存在している事例としては、従業員がいわゆるユニオン(合同労組)という外部の労働組合に加入している事例が多くなっている。
すなわち、従業員がユニオン(合同労組)に加入し、ユニオン(合同労組)が組合員である従業員の代わりに対象会社に対して団体交渉を申し入れて、労働環境の改善や不当な行為の停止、未払賃金・退職金等の支給を要求することが多くなっている。
また、このようなユニオン(合同労組)は、従業員の代わりに対象会社に対して団体交渉を申し入れて、労働環境の改善や不当な行為の停止、未払賃金・退職金等の支給を要求するために、従業員から依頼を受けている形であり、対象会社に対して、強く、労働環境の改善や不当な行為の停止、未払賃金・退職金等の支給を要求することが多く、対象会社のオーナーとしては、ユニオン(合同労組)に対する対応に非常にエネルギーを費消することとなる。
ユニオン(合同労組)としても、対象会社の経営陣に、多大なエネルギーを費消させ、困惑させることによって、自分の不当な要求を飲ませようとするところも多いように見受けられる。
また、ユニオン(合同労組)には、対象会社の多数の従業員を巻き込み、対象会社の事業の運営に大きな支障が生ずることを厭わず権利行使を行ったり、対象会社の従業員を取り込み、ユニオン(合同労組)の思い通りに対象会社の事業の運営を行える状態としてしまい、対象会社の経営をほとんど支配してしまうこともある。
そのようなことになってしまっては、もし仮に、買主が、事業承継M&Aにより、対象会社を買収したとしても、ユニオン(合同労組)の存在によって、実質的に、対象会社の経営支配権を確立することができないことが明らかであったり、対象会社の経営支配権を確立することが困難であったり、大きな支障になったりするような場合、事業承継M&Aの実現は非常に困難となる。
対象会社にユニオン(合同労組)が介入していなくても、対象会社に、ストライキ(同盟罷業)、ピケッティング(就労阻止等)、サボタージュ(同盟怠業)などの労働争議が存在する場合も、上記同様に、買主から見て、対象会社の企業価値は大幅に損なわれている状態であり、買主としては、事業承継M&Aを実行したとしても、想定した効果は得られないものとして、事業承継M&Aの実現は非常に困難になってしまう。
また、対象会社にこのような労働争議や労働組合が存在する場合、M&A専門の弁護士に依頼し、対象会社の正常化を実現してからでないと、事業承継M&Aの遡上には乗りません。
したがって、事業承継M&Aにおいては、株式譲渡契約書において、労働争議の不存在や労働組合の不存在について、売主に表明保証してもらう必要がある。
第9号(2)は、未払賃金・退職金等の不存在に関する表明保証である。
未払賃金・退職金等について
労働関連法については、近時、労使紛争の中でも、未払賃金・退職金等に関する紛争が特に多くなっており、実際、事業承継M&Aに際しても、未払賃金・退職金等に関する紛争は頻発している。
また、近時、消費者金融業者に対する過払い金請求事案の減少により弁護士が従業員の未払い残業代請求を主たる業務に据え事業運営を行っており、未払賃金・退職金等の請求の事案が急激に増加している。
事業承継M&Aの対象となる中堅企業・中小企業においては、労働時間の管理が十分でない会社、未払賃金・退職金等がしっかり支払われていない会社が多く、就業規則の作成や三六協定の届出が行われていない会社もまだまだ存在する。また、一見、労働時間の管理が十分であり、未払賃金・退職金等がしっかり支払われていると思われる会社であっても、労働関連法の解釈や、厚生労働省の指導を正確に理解していない結果、対象会社に未払賃金・退職金等が発生しているケースは非常に多く、これが対象会社の潜在債務となっている例が少なくない。
事業承継M&Aについては、対象会社のオーナーや経営陣が変更になる、対象会社の従業員にとっても一大イベントであり、事業承継M&Aに伴い対象会社に対する忠誠心が薄れたり、対象会社の旧オーナーや経営陣が変更になることにより、従業員の勤労意欲や仲間意識が減退するなどし、退職する従業員も多く、また、それが理由で、対象会社に対して、未払賃金・退職金等の請求を行う元従業員も急増することがありうるし、実際に数多くそのような事態が発生している。
したがって、事業承継M&Aにおいては、株式譲渡契約書において、未払賃金・退職金等の不存在について、売主に表明保証してもらう必要がある。。
みなし残業代制度の問題について
特に、事業承継M&Aの対象となる中堅企業・中小企業においては、適切にみなし残業代制度を導入していないために、未払賃金・退職金等が発生してしまっていることが多い。
すなわち、対象会社としては、一定時間数の残業代が、基各種手当、固定残業代として支払い済み若しくは基本給に包含されていると思っているところ、法令上、実際には、みなし残業代制度導入の要件を満たしていないために、未払賃金・退職金等が発生していると評価される場合が多い点について、留意する必要がある。
対象会社が、定額の時間外手当を、基本給や他の手当と明確に区別した手当として支給したと思っている場合において、①当該手当が実質的に時間外労働の対価としての性格を有していること、②定額残業代として労働基準法所定の額が支払われているか否かを判定することができるよう、その約定の中に明確な指標が存在していること、③当該定額の時間外手当が労働基準法所定の額を下回るときは、その差額を当該賃金に支払い時期に精算するとの合意が存在するか、あるいは少なくともそうした取り扱いが確立していることという要件が不可欠とする裁判例(イーライフ事件、東京地裁平成25年2月28日判決)が存在し、対象会社において導入されているみなし残業代制度が適法かどうかの、実務上の指標となっている。
また、テックジャパン事件最高裁判決(最高裁平成24年3月8日判決)の櫻井裁判官の補足意見は、「便宜的に毎月の給与の中にあらかじめ一定時間(例えば10時間分)の残業手当が算入されているものとして給与が支払われている事例もみられるが,その場合は,その旨が雇用契約上も明確にされていなければならないと同時に、支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示されていなければならないであろう。
さらには、10時間を超えて残業が行われた場合には当然その所定の支給日に別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにされていなければならないと解すべきと思われる」としており、この点も、対象会社において導入されているみなし残業代制度が適法かどうかの、実務上の指標となろう。
なお、対象会社が、残業代が基本給等に支払われていると思っている場合は、①基本給のうち時間外手当に当たる部分を明確に区分して合意し、かつ②労働基準法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払い期に支払うことを合意した場合のみ、当該定額分を割増賃金とできるとするのが判例(高知県観光事件、最高裁平成6年6月13日判決)があり、この点も、対象会社において導入されているみなし残業代制度が適法かどうかの、実務上の指標となる。
すなわち、事業承継M&Aの法務デューデリジェンスにおいて、対象会社にて、実際に、残業代が、定額の時間外手当として支給されている場合、上記要件を満たさない場合がしばしば見られるため、対象会社の雇用契約書・就業規則(賃金規定を含む)、賃金台帳、給与明細等を確認する必要がある。
管理監督者の問題について
労働基準法上、時間外労働や休日労働等を行った労働者に対しては、割増手当を含めた賃金の支給が必要とされるが、労働基準法第40条第2号において、「監督若しくは管理の地位にある者」(いわゆる管理監督者)に該当する場合は、上記手当を支給の対象外となるとされている。
しかしながら、裁判例上、この管理監督者に該当するか否かは、①事業主の経営に関する決定に参画するなど職務内容の重要性、②自己の出勤退勤などの労働時間について裁量権の有無、③管理監督者として処遇されるにふさわしい賃金上の処遇されていること、を主たる要素として判断するのが裁判例の流れである。
すなわち、労働基準法上の「管理監督者」と、実務上の「管理職」とは、必ずしも、同義ではないのである。
したがって、対象会社において、課長などの役職が付され管理職として取り扱われている従業員について、残業代の支給が不要となるわけではない点について留意する必要がある、
未払賃金・退職金等の偶発債務性について
対象会社に未払賃金・退職金等が存在するからと言って、直ちに、従業員が、対象会社に対して、未払賃金・退職金等請求を行うわけではなく、必ず、対象会社に損害が発生するわけではない。
すなわち、従業員が、対象会社に対して、未払賃金・退職金等の請求を行うか否かは、その従業員次第であり、対象会社との関係性などにも影響されるところであるし、従業員が対象会社に未払賃金・退職金等の請求を行った場合、一般的には、対象会社に居づらくなることから、多くの場合は、対象会社に在職中は、未払賃金・退職金等の請求を行うことはなく、対象会社を退職したのち、対象会社に対して、未払賃金・退職金等の請求を行うのである。
事業承継M&Aに関しては、事業承継M&Aに際して退職した元従業員のみならず、事業承継M&Aの相当以前に退職した元従業員が、対象会社が事業承継M&Aを行ってオーナーが変更になったことを知って、対象会社に対して、未払賃金・退職金等の請求を行うことも多い。
なお、未払賃金の請求権の時効は2年であることから、2年以上前に退職した元従業員は、未払賃金の請求を行うことはできず、退職して暫く経っている元従業員も、未払賃金は少額になってしまっているであろうから、未払賃金の請求を行うケースはそれほど多くないものと思われる。
ただ、近時、報道によると、未払賃金請求権の時効が2年から5年に延長する法改正が検討されているとのことであり、この点は非常に注意が必要であり、この法改正が実現した場合、事業承継M&Aに対する大きな障害となることが危惧されている。なお、未払退職金の時効は5年であることから、対象会社に未払退職金が存在している場合は、特に留意が必要である。
⇒元従業員の未払い残業代でお困りの方はこちら!
第9号(3)は、労働関連法規の遵守に関する表明保証である。
労働関連法規は多種に渡っている。
労働基準法、最低賃金法、パートタイム労働法、男女雇用機会均等法、障害者雇用対策法、高齢者雇用促進法、労働安全衛生法、など多数の法律が存在する。
労働基準法上、使用者は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに、所定の事項を記載した就業規則を作成し、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられている(労働基準法89条)、また、常時10人以上の労働者を使用する会社において、使用者が就業規則を作成・変更する場合には、その内容について、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、それがない場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聴取し、その意見を記載した書面を労働基準監督署長へ届出の際に添付する必要がある。また、使用者は、所定の方法により就業規則を労働者に周知させなければならない点(労働基準法106条)も、留意が必要である。
また、労働基準法上、1日8時間週40時間を超える労働は時間外労働、週休制の法定基準による休日における労働は休日労働、とされており非常事由による場合を除いては、事業場における時間外労働・休日労働の労使協定(いわゆる三六協定)を締結し、それを労働基準監督署に届出た場合は、その協定に定めるところにより労働時間を延長し、又は休日に労働させることができるとしている。
この点、時間外労働・休日労働を行わせることができる範囲は、あくまで三六協定記載の範囲に限られる点に留意が必要である。
なお、従来は、行政通達により三六協定では、1ヶ月あたり45時間・1年間360時間などの限度時間が定められていたものの、定められている限度時間数を超えた三六協定の締結・届出が明確に禁止されていなかったこと、特別条項での時間延長に関し、限度が定められていないことが問題点とされていたが、政府のすすめる働き方改革の一環による労働基準法改正により、一定の事業を除き、時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、単月100時間(休日労働含む)、年720時間(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定することが必要となる点に留意が必要である(なお。改正法の適用は、大企業については2019年4月1日、中小企業については2020年4月1日からの予定である)。
最低賃金法については、地域別最低賃金として、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められている。その他、特定最低賃金として、特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されている。なお、精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者など一定の場合は、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたことを条件に労働能力等を考慮して定めれた一定率減額した金額が最低賃金となる。
障害者の雇用の促進等に関する法律上、一定数以上の労働者(なお、一定の短時間労働者は0.5人と換算する)を雇用する一般事業主は、一定の割合の障害者雇用率を達成する必要があり、毎年6月1月時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければならない(障害者の雇用の促進等に関する法律43条)。また、常時100人を超える労働者を雇用する事業主は、法定の障害者雇用率が未達成の場合は、障害者雇用納付金を納付する必要がある。
高齢者等の雇用促進等に関する法律は、使用者に対し、①定年年齢の65歳以上への引き上げ、②65歳までの継続雇用制度導入、又は③定年制度廃止、のうちのいずれかの措置を行うことを使用者に義務付けている(高齢者等の雇用促進等に関する法律9条)。これに違反した使用者に対しては、労働局からの指導・勧告の他、事業者名の公表等の制裁が科されうる(高齢者等の雇用促進等に関する法律10条)労働安全衛生法は、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、事業場内における責任体制の明確化、事業者の自主的活動の促進の措置など労働災害の防止に関する総合的計画的な対策の促進により、職場における労働者の安全と健康の確保すること快適な職場咸鏡の形成の促進を目的としている(労働安全衛生法1条)。
労働災害がひとたび発生すると、労働安全衛生法違反等により、刑事責任が追及されうるほか、事業場の設備の使用停止命令、作業中止命令などの行政処分が下されることがある。
また、労働災害が発生すると労働者災害補償保険法に基づいて必要な保険給付が行われるものの、労災保険において労働者の損害のすべてが補償されるわけではなく、労働者ないしその家族より雇用契約上の安全配慮義務違反を根拠として損害賠償を請求され、義務違反の認定にあたっては労働安全衛生法を遵守していたかどうか重要な判断材料とされる点、留意が必要となる。
労働安全衛生法は、その他、事業場の規模に応じて、安全衛生管理に関する責任者や担当者、産業医を選任すること、安全委員会や衛生委員会等設置運営することを義務づけている。
また、労働安全衛生法は、労働者の経験や知識不足による労働災害の発生の防止のため、①雇入れ時の教育(労働安全衛生法59条1項)、②作業内容変更時の教育(労働安全衛生法59条2項)、③一定の危険業務を実施する者に対する特別の教育(労働安全衛生法59条3項)、④職長の教育(労働安全衛生法60条)、⑤安全衛生水準向上のための教育(労働安全衛生法60条の2)の実施を義務付けている。
また、労働者の健康の保持・増進の観点から、常時使用する労働者を雇い入れた場合には、業種及び規模を問わず、雇入れ時及び定期的な医師による健康診断を実施しなければならない。
さらに、一定の有害業務に従事する労働者に対しては、医師による特殊健康診断、歯科医師による特殊健康診断を実施する必要がある。健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者に関しては、当該労働者の健康を保持するための必要な措置について医師又は歯科医師の意見を聴取しなければならず、同意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施。施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他適切な措置を講じなければならないとされている。
また、事業者は、週単位の時間外労働が1ヶ月100時間を超え疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、医師による面接指導を行い、その結果を記録し、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴取し、同意見を勘案して必要があると認められるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回収の減少などの必要措置をこうじなければならないとする。また、事業者は、労働者に対し、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う必要がある。
その他にも男女雇用機会均等法、育児介護休業法、外国人の従業員が存在する場合の出入国管理及び難民認定法など労働関連法規は多岐にわたる点、留意する必要がある。
したがって、事業承継M&Aにおいては、株式譲渡契約書において、労働関連法規の遵守について、売主に表明保証してもらう必要がある。
年金及び保険等対象会社は、社会保険料その他の保険料・年金掛金等について、期限までに適法に支払われている。対象会社は、加入する社会保険組合や年金基に積立不足など存在せず、保険料・年金掛金等について、特別掛金他の追加資金拠出義務が発生することもない。 |
第10号は、年金及び保険等に関する表明保証である。
年金及び保険等の未払いについて
対象会社において、本来支払うべき社会保険料その他の保険料・年金掛金等を支払っていない場合、対象会社においては、未払い社会保険料等の潜在債務を有することとなりうる。
社会保険とは、日本においては、医療保険(健康保険)、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険の5種類がある。医療保険(健康保険)としては、サラリーマンが加入する健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険など)、個人事業主などが加入する国民健康保険など、年金保険としては、サラリーマンが加入する厚生年金、個人事業主が加入する国民年金などがある。
対象会社は、事業主として、これら社会保険料のうち、医療保険(健康保険)、介護保険、年金保険については、事業主負担分として従業員の社会保険料等の半分を負担することとされており、雇用保険については、一部保険料は事業主が全額負担、残部の保険料は事業主と従業員が折半で負担することとなっている。
また、事業主は、従業員負担分の残りの半分についても従業員の給与から源泉徴収義務が存在する。労災保険については、保険料の全額を事業主が負担するものとされている。
なお、介護保険については、介護保険料の徴収の方法は65歳以上(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満(第2号被保険者)によって異なり、40歳以上65歳未満の者は、加入している医療保険によって料率は異なるものの、医療保険の保険料に上乗せして徴収される。
したがって、対象会社に社会保険料等の未払いが存在する場合、事業主負担分のみならず、従業員負担分についても未払いになっていることが多い。
資金繰りが悪化している会社においては、従業員の給与から、社会保険料等の従業員負担分を控除しておきながら、社会保険料等を納付していないのである。
そのような場合、対象会社は潜在債務を負担しているということとなり、対象会社の企業価値が毀損されているということとなる。
従業員の承諾に基づく社会保険等への未加入について
また、従業員によっては、社会保険料等の従業員負担分を支払わず手取り給与の額を最大化しようとして、敢えて社会保険等に加入しないことがある。
すなわち、会社が事業主負担分を負担することを避けるため従業員を社会保険等に加入させない場合のみならず、従業員が本人負担分を負担することを避けるため、従業員から会社に要請して、社会保険等に加入しない場合がある。この傾向は、飲食業などパートタイマーが多い業界や製造業など外国人労働者が多い業界に多いように思われる。
すなわち、主婦などのパートタイマーはそもそも配偶者の社会保険等に加入しているため、あえて勤務先の社会保険等に加入して従業員負担分を負担することを嫌う傾向にあり、かつ外国人労働者もいつ帰国するか分からないと考え、帰国してしまえば、日本政府から最終的に年金などを得られることはなく実質的に掛け捨てとなってしまうことから、敢えて社会保険等に加入したくないと考えることが多いように思われる。
事業主である対象会社としては、このような従業員の意向を踏まえ社会保険等に加入しないという扱いとすることもままあるようであるが、それは違法であるのみならず、もし実際に労災が発生したり、その者が傷病にかかるなどした場合、社会保険等が支給されない結果、その従業員が十分な稼働ができなくなるのみならず、未払い社会保険料等が存在することが発覚し、年金事務所から、対象会社に対して、納付を求められたり、対象会社が、本来、その従業員に対して、社会保険等から支給されるはずであった保険金相当額を負担しなければいけなくなる可能性がある。
したがって、事業承継M&Aにおいては、株式譲渡契約書において、売主に未払い社会保険料等が存在していないことを表明保証して頂く必要がある。
社会保険等への未加入と保険料等の追徴
労働保険については、事業主が、行政機関から労働保険関係の成立手続きを行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に手続きを行わない場合、労働保険料の認定が行われ、過去分については、遡って労働保険料が追徴される(労働保険の保険料の徴収等の手続きに関する法律19条5項、21条1項)
労災保険については、事業主が、労災保険への成立手続を行っていない期間中に労働災害が生じ、労災保険保健給付を行った場合、最大2年間遡った労災保険料と追徴金が徴収されるほか、労働局職員あるいは労働基準監督署監督官からの勧奨・指導を受けていたにも拘わらず、労災保険に加入をしていない場合。
事業主の故意による未加入と判断され、労災給付金額の全額が徴収されることになり、労働局職員あるいは労働基準監督署の監督官から加入勧奨・指導ないまま、労働保険の適用事業となってから(労働者を雇用してから)1年を経過している場合は、事業主の重大な過失と判断し、労災保険給付の40%が徴収されることになる。
雇用保険については、保険関係が成立しているにも関わらず手続きを行わない事業主には、労働保険料の認定が行われ、過去に遡って労働保険料が徴収されるとともに追徴金が徴収されうる点(労働保険の保険料の徴収等に関する法律19条5項、21条1項)、被保険者であるにもかかわらずその届出をしない場合は刑罰の対象となる点(雇用保険法83条)、留意する必要がある。
厚生年金については、加入対象の労働者を厚生年金に適切に加入させていない場合には刑罰が科されうる(厚生年金保険法第102条)点、また、未加入により本来受給できる厚生年金が減少したとして、労働者から損害賠償請求がされうる点につき留意が必要である。
医療保険(健康保険)については、医療保険(健康保険)料の未納は、過去2年分は追徴の対象となる点(健康保険法193条)、事業主は被保険者であるにもかかわらず届出を行っていない場合は刑罰を科されるうる点(健康保険法208条)、留意する必要がある、
パートタイマーの社会保険等の加入義務について
正社員については、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険に加入する義務があるのは当然であるが、パートタイマーについては、健康保険、年金保険、雇用保険、労災保険に加入する義務があるか否かについては、健康保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険ごとに要件が異なっており、要件を満たしていない従業員については、必ずしも健康保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険に加入する必要はない点留意する必要がある。
労災保険について
労災保険については、労働者を使用する事業者は、全て労災保険への加入を強制されている点につき留意する必要がある(ただし、国の直営事業及び官公署の事業は適用外、個人経営の農林・畜産・水産の事業で小規模のものは暫定任意適用事業とされる)。すなわち、一人で労働者を雇用する事業者は、事業が開始した日の保険関係が成立するとされている(労働災害者保健法3条1項、6条)点に留意する必要がある。
雇用保険について
雇用保険については、ごく小規模の個人経営の農林、畜産、水産事業を除いた労働者を使用する全事業が適用対象となり、事業が開始された日にその事業について保険関係が成立する。雇用保険については、適用対象事業を行う事業主に雇用されている者は、原則として被保険者となる(雇用保険法4条1項)が、次のいずれかに該当する者は適用除外とされている(雇用保険法6条)。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)
- 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
- 季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の期間を定めて雇用されるもの又は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
- 学校教育法上の学校の学生又は生徒であって、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
- 船員であって、漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く)
- 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定める者
厚生年金について
厚生年金については、労働者は、適用事業者に使用されるに至った日から被保険者としての資格を取得する(厚生年金保険法13条1項)。厚生年金への加入が義務付けられる適用事業所とは、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用する者及び、厚生年金法第6条1項1号に規定された事業の使用者であって、常時5人以上の従業員を使用する者、船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶のいずれかに該当する者をいう。事業者が法人であれば、労働者の人数、事業の内容を問わず、適用事業所となる。
厚生年金の被保険者は。適用事業所に使用される70歳未満の者をいう。また、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者についても、厚生労働大臣の認可を受ければ、被保険者となることができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、適用が除外される。
- 臨時に使用される者(船舶所有者の雇用される者を除く)であつて、日々雇い入れられる者(ただし、雇用が1ヶ月を超える場合を除く)若しくは2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(ただし、所定の期間を超えて雇用されるものは除く)
- 所在地が一定しない事業所に使用される者
- 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員、継続して4ヶ月を超えて使用されるべき場合を除く)
- 臨時的事象の事業所に使用される者(継続して6ヶ月を超えて使用されるべき場合を除く)
- 1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬について、厚生労働省令で定めるところにより、算定した額が、8万8000円未満であること。
ニ 学校教育法規定する高等学校の生徒、同法に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
すなわち、事業承継M&Aの法務デューデリジェンスにおいて、主として加入の要否が問題となる短時間労働者については、当該事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上であれば、厚生年金の加入の対象となる。
また、当該事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間若しくは1ヶ月の所定労働日数が4分の3未満であったとしても、厚生年金の被保険者501人以上の企業(特定適用事業所)の場合、①所定労働時間が週20時間以上、② 1年以上雇用が見込まれる、③賃金の月額が8.8万円以上、④学生でない、という要件を満たす場合は、短時間労働者であっても、厚生年金の加入の対象となる。
ただし、厚生年金の被保険者が500人以下の事業所の場合は、現時点では加入の対象とはなっていないものの、上記①から④の要件を満たす短時間労働者については、労使の合意によって加入の対象なりうる。
医療保険(健康保険)について
医療保険(健康保険)については、労働者は、適用事業者に使用されるに至った日から被保険者としての資格を取得する(健康保険法35条)。健康保険への加入が義務付けられる適用事業所とは、①国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用する者、及び、②厚生年金法第6条1項1号に規定された事業の使用者であって、常時5人以上の従業員を使用するもの、③船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶のいずれかに該当するものをいう。事業者が法人であれば、労働者の人数、事業の内容を問わず適用事業所となる。
適用事業所で使用される者は、原則として被保険者となる(健康保険法3条1項本文)が、次のいずれかに該当する場合は、日雇特例被保険者となる例外的な場合を除き、被保険者となることができない(健康保険法3条2項、健康保険法3条1項但書)。
- 船員保険の被保険者
- 臨時に使用される者であって、日々雇い入れられる者で1ヶ月を超えない者又は2ヶ月以内の期間を定めて使用される者で所定の期間を超えない者
- 所在地が一定しない事業所に使用される者
- 季節的業務に使用される者(継続して4ヶ月を超えて使用されるべき場合を除く)
- 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除く)
- 国民健康保険組合の事業者に使用される者
- 後期高齢者医療の被保険者等
- 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)
- その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと
ハ 報酬について、厚生労働省令で定めるところにより、算定した額が、8万8000円未満であること
ニ 学校教育法規定する高等学校の生徒、同法に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること
すなわち、事業承継M&Aの法務デューデリジェンスにおいて、主として加入が問題となる短時間労働者については、当該事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が4分の3以上であれば、当該短時間労働者は健康保険加入の対象となる。
また、当該事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間若しくは1ヶ月の所定労働日数が4分の3未満であったとしても、健康保険の被保険者501人以上の企業(特定適用事業所)の場合、①所定労働時間が週20時間以上、②1年以上雇用が見込まれる、③賃金の月額が8.8万円以上、④学生でない、という要件を満たす場合は、短時間労働者であっても、医療保険(健康保険)の加入の対象となる。
ただし、通常の労働者及びこれに準ずる者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であり、かつ、その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者をいう)の総数が常時500人以下の事業所の場合は、現時点では加入の対象とはなっていないものの、上記①から④の要件を満たす短時間労働者については、労使の合意によって加入の対象なりうる。
⇒M&Aトラブル・表明保証違反・コベナンツ違反・M&Aの損害でお困りの方はこちら!